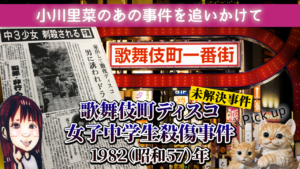いじめは今日でも重要な社会問題、教育問題ですし、ネットいじめなど新たな形態のいじめも起こっていますが、かつていじめが学校で猛威をふるっていたと言っても過言でない時期がありました。

上の表は、文科省が行なった「いじめ」と認知された件数の調査結果で、この時は公立の小・中・高校だけを対象にしていました。
一見して、昭和60(1985)年度(左端)の件数が飛び抜けて多いと分かります。
そのはずで、実はこの調査はこの年度から新たに始められたのです。つまり、1970年代後半から問題として現れた学校でのいじめが、1980年代(昭和50年代後半)に入って急増し、自殺者が相次ぐなど深刻な事態になったことを受けて早急な防止対策が求められ、そのための実態把握を目的にこの調査(現在の正式名称は、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)が行われるようになったのです。
いじめが、単なる「悪ふざけ」ではすまないまでの内容になると、加害者にとっては「一時の遊び」に過ぎなくても、被害者にとっては「一生の恨(うら)み」となっても不思議ではありません。時間とともに薄れていく「恨み」もありますが、心の奥底まで抉(えぐ)られた痛みが怨念となって、時間が経つほどに深く根を下ろしついに爆発することもあります。
1991(平成3)年1月に佐賀県で起きた同窓会大量殺人未遂事件があります。

朝日新聞(1991年1月22日)
赤司良治とは
この事件で「中学時代にいじめられた仕返しをしたかった」と供述し、爆発物取締罰則違反・現住建造物等放火予備・殺人予備の罪で逮捕されたのは、赤司(あかし)良治(当時27歳)という人物でした。

赤司は1964(昭和39)年、中学教師の両親(父は英語教諭で母は音楽・養護教諭)の元に佐賀県で生まれました。
彼は地元の小学校に入学しますが同級生になじめなかったようで、小学3年生の時に両親が彼を学区外の小学校に転校させ、中学校もそのまま学区外の上峰(かみみね)村立上峰中学校に進学します。
時期としては1977(昭和52)年〜1979(昭和54)年ですので、最初に述べたように学校でのいじめが問題として広がり始めたころです。
中学時代に受けたいじめ
この中学校には、赤司の父親も教師として勤務していましたが、ここで赤司は同級生からひどいいじめに遭ったのです。
断片的に伝えられるいじめの内容としては、ヘッドロックをかける、頭にパンチを入れる、掃除用具入れに閉じ込める、ドブ川の水を飲ませる、女生徒の前で裸にさせるといった、暴力・強要をして嘲笑するものだったようです。
体は小さかったものの、やられたらカッとなって言い返す「強情」な赤司に対して、「生意気だ」ということで、いじめはエスカレートしていきました。
赤司は、いじめについて教師や両親に何度も訴えたようです。しかし、「お前にも悪いところがあるからだ」とか「きちんと立ち向かえ」と説教されるばかりで、まったく取り合ってもらえませんでした。
同じ中学校に勤務していたことで、父親もむしろ「事なかれ」の姿勢に終始したようです。
復讐への意志
誰からも救いの手を差し伸べられなかった赤司の心に、いじめた同級生や訴えを無視した教師たちへの「一生の恨み」が蓄積したことでしょう。
赤司が「いじめへの復讐」をはっきり具体的に考え始めたのは18歳、高校を卒業した時からのようですが、佐賀県立神埼農業高校食品化学科から熊本工業大学応用微生物工学科に進学し、卒業後には3つの化学関連企業に勤めるなど一貫して化学畑の道を進んだのも、化学薬品の知識と扱いに習熟し試薬を入手するという、毒物を用いた復讐への準備を意識したものでした。
さらに彼は、後で述べる時限爆弾の製造のために危険物取扱者甲種の資格(すべての危険物が取り扱える最上位の資格)も取得しています。
ですから、中学を卒業した時点ですでに、赤司の心の中には「復讐」の二文字が刻み込まれていたのではないでしょうか。
復讐の機会をつくる
同級生や「恩師」たちが一堂に会する復讐の機会として赤司が考えたのは同窓会でした。卒業後初めて開く同窓会の呼びかけ人となったのは赤司自身で、事件前年(1990年)の夏ごろから準備を始めます。
アンケートハガキを送ってできるだけ多くの人が集まれる日と場所を調べ、返事のない人にはわざわざ電話をかけて聞いたそうです。
その結果、1991(平成3)年1月2日の午後5時から、佐賀市内の旅館で同窓会を開くことが決まり、赤司はそれに向けて着々と準備を進めます。

同窓会が開かれた旅館
復讐の方法
同窓会には約50人の同級生と教師が出席することになっていました。それだけ多くの人を殺害する方法として赤司が考えたのは、ヒ素を混ぜたビールを飲ませること、そして時限爆弾を爆発させることの二つでした。
彼はそれらを、勤めていた会社を退職した1990年11月ごろから、当時住んでいた埼玉県の自宅で作ります。
まず、味ですぐに気づかれないよう、わざわざ珍しい東欧産のビールを買い、分からないように栓を開けて、コップ一杯で致死量となるほどのヒ素を混入させたものを21本作ります。
会場の旅館も飲み物の持ち込みが自由にできるところを選び、大晦日に旅館に運び込んでいます。
もう一つは爆弾で、赤司は、塩素酸カリウムとアルミニウム粉末を混ぜた火薬にガソリンを可燃物とした爆弾を3つ作り、そこにタイマーと電池と豆電球で作った時限発火装置をつけたものを用意します。
それは、数十人を殺傷可能な威力を持つものでした。
赤司は、爆弾を木箱に入れ、ヒ素入ビールと共にワゴン車に積んで、12月28日に佐賀の実家に帰ります。
犯行計画の発覚ヒ素入りビールをひと足先に旅館に運び込んだ12月31日、実家に戻った息子の様子がおかしいのを心配した母親の克江さんが赤司の荷物を調べたところ、「決行の時は来た」という「序」で始まる殺害計画の手記を発見し驚きます。


『週刊ポスト』(1992年)『週刊ポスト』誌によるとこの「手記」は、「B5版ワープロ用誌9枚の分量。ハードボイルド風の文体を装った文章で、犯行計画直前の一昨年[1990年]12月29日、大学時代の友人にワープロで口述筆記させたもの」とのことです。手記の内容に驚いた母親は、年が明けたばかりの深夜午前1時に警察に届け出ます。旅館を捜索した警察は、赤司が運び込んだばかりのヒ素入りビールを発見し押収するとともに、2日朝に赤司の身柄を拘束して取り調べを行いました。その結果、同窓会が開かれるまさにその日に旅館に持ち込んで宴会場に仕掛けようとしていた爆弾が、自宅にとめたワゴン車にあると判明したため、警察官が押収に向かったところ、ちょうど同窓会が盛り上がる時間にセットされた時限爆弾が時間どおりに爆発し、3人の捜査員が重軽傷を負ったのです。そのころ、同級生40数名に元教師5名が参加した同窓会は、事件については何も知らないまま予定どおり開かれ、参加者たちは12年ぶりの再会の時を楽しみました。ただ、会の開催を呼びかけお膳立てをした幹事の赤司良治の姿が見えないことに「どうしたのだろう」という声が出たようですが、「急用で来られなくなったらしい」ということで、それ以上に気にとめられることはなかったようです。その時、かつて自分たちが彼におこなったいじめについて思い起こした人はどれくらいいたでしょうか。
逮捕と裁判
赤司は、精神障害が疑われるということで措置入院させられ精神鑑定されますが、責任能力があると判断されたことから、1月22日になって爆発物取締罰則違反・現住建造物等放火予備罪・殺人予備罪の容疑で逮捕されました。起訴された赤司に対して佐賀地方裁判所は、1992(平成4)年1月23日、懲役6年の実刑判決を下します。殺害行為が実行以前に阻止された「予備罪」に対する罰としてそれは、警察官が負傷したこともあってか、異例に重いと弁護側は主張し控訴しました。しかし、同年7月14日に福岡高等裁判所は控訴を棄却し、懲役6年の刑が確定しました。
小川里菜の目
いじめがどれだけ人の心を深く傷つけるか、被害者の一生を台無しにしてしまうことがあるほど罪深いものであることをあらためて思い知らされる事件です![]()
最初に見たように、1980年代後半になるとようやくいじめが深刻な問題として認識されるようになり、文科省も対策に取り組み始めますが、赤司良治が被害にあった1970年代後半はまだいじめに対する認識が教師・学校にも、また生徒たち自身にも甘く、仲間内の「悪ふざけ」程度に受けとめられることが多かったのです。
しかしそれは、加害者や第三者にとっての話であって、赤司のような被害にあった生徒にとっていじめはまさに「地獄の苦しみ」だったことでしょう。
それだけの苦しみを与えた加害者に対し、謝罪や罪に見合った処罰を求めることは、まったく正当な要求であることは間違いありません。
とはいえ、いじめの被害に対して加害者に個人的に復讐することが適切な正義の行使になるとは小川には思えません![]()
この事件でも、仮に赤司の計画どおり事が運んで、ヒ素入りビールや爆弾の爆発とガソリンによる火災で、いじめ加害の軽重にかかわらず多くの元同級生・教師が無差別に重軽傷を負いまた命を落としたとしたら、それをかつてのいじめでの「罪に見合った適切な罰」すなわち「損なわれた正義の回復」と認めることはとてもできない大惨事となったことでしょう![]()
赤司が中学時代に受けたいじめへの復讐に一生を賭けようと思ったのには、もちろんその時の体験の記憶がいつまでも彼の心を蝕(むしば)んだこともあったでしょうが、もう一つ見逃せない事情がありました。
赤司は「手記」に、「大学に入学した時、虐げられた今までの人生とはうってかわって楽園がやってきた。大学とはこんなにいい所か!」と書いています。このように彼の大学生活は、高校までの学校生活とは違って、とても楽しく充実したものだったようです![]()
もしそれがそのまま続いたとしたら、受けたいじめを許せない気持ちは消えないとしても、ただ過去に縛られ続けるのではなく、自分の力で切り開くことのできる未来に目を向けての一歩を踏み出すことができたかもしれません。
ところが不運なことに、1984(昭和59)年、赤司が大学生であった20歳の時に、B型肝炎ウィルスのキャリアであった父親が、肝硬変により病死したのです。まだ50歳代早々の若さだったと思われます。
しかも赤司が23歳の時に、自分も父親と同じB型肝炎ウィルスのキャリアであることが明らかになります。
おそらく彼はそこで、自分も父親と同様に長くは生きられないと、未来が閉ざされたような絶望を味わったのではないでしょうか。
そのことが、ようやく未来へと向きかけた彼の心を、もう一度過去へと引きずり戻したように思えてならないのです![]()
「手記」に彼は、「B型肝炎を患い、薬づけの毎日を送り、ちっとやそっとの投薬量では効かない体になっている」と書いています。
もう未来が失われてしまった自分にとっては、「私を虐待し、虫けらの様に扱った愚者共」に制裁を加え道連れにして死ぬことだけが、唯一自分の人生を意味あるものにする道だと、赤司が思い詰めたとしても無理はありません。
また、いじめを受けていた時に赤司は、誰からもその苦しさや悔しさを理解されず、救いの手を差し伸べてもらえない孤独に、いじめ以上の絶望を感じていたのではないかとも思います。
そしてその孤独の哀しみを彼は、不治の病という不運が加わることによってあらためて募らせ、せめて自分をいじめた者たちや見捨てた者たちに復讐を遂げてから人生に幕を引くという彼なりの決着のつけ方にのめり込んでいったのではないでしょうか。
客観的に見れば、そうした赤司の行動は決して賢明とは言えず、むしろ狂気に近いものですらあったでしょう。しかし、人間の自尊心を踏みにじる行為と、どんな救いもないと思わせる孤独が、人をそこまで追い詰めてしまうという事実に対し、私たちはもっと敏感でなければ、と思う小川です![]()
赤司が親や教師にいじめられていると訴えても、「お前にも悪いところがある」と取り合ってもらえなかったことは先に書いたとおりです。同じようにネット上でも、「いじめられた側にも問題があった」と言う人がよくいます。
それに対して小川が言いたいのは、いじめを正当化する理由などどこにもないということです。
人はみな欠点や弱点を持ち、しばしば過ちさえ犯してしまうものです。「約束を破った」「生意気だ」「考えが合わない」「変わっている」などなど、相手を気に入らない(ムカつく)理由はいくらでもあげることができます。
それに対しては、事の重要性と相手との関係性に応じて、「違いを受け入れる」「自分自身を振り返る」「本音で話し合う」「厳しく批判する」といったことから「相手と距離を置く」ことまで、いろいろな対応がありうるでしょう。しかしその中に、「いじめる」という選択肢はどこを探してもないと小川は思うのです。
子どもにそんなことは分からないと言うなら、分かるようにそれを教えるのは周りの大人たちの責任です。
ですからいじめの理由は、被害者の中にではなく、加害者の側にこそ求めるべきものなのです。